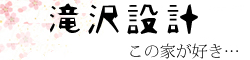自由な発想で新築住宅はここまでできる
前回、「蔵の無い部分の天井高が不必要に高い」という「蔵」の大きな欠陥をお話ししました。
でもそれは、その高い天井がなくてはならないものになるように意味を与えると、今度は突如として家全体が機能し始めます。
活用法1、「そこだけミニ2階建空間」
当面は客間として高い天井を満喫し、将来子供用に部屋を2つに割る。平面的な広さだけを見ると小さいが、天井高が十分にあるのでロフトを造って2層とし、そこで就寝すれば、その下全てを利用でき子供部屋としての機能が確保できる。いってみれば「そこだけミニ2階建空間」です。
そしてこの活用法には将来への布石も打ってあります。 お子様が独立された後は、「そこだけ2階建空間」を撤去してセカンドライフの趣味や多目的なスペースとして、天井の高い大空間は生活におおいに可能性を付与してくれることでしょう。
活用法2、「完全2段収納」
ウォークインクローゼットの上をロフトとして造り、高い天井高の全てを2段収納として使い切る。
これなら、「蔵」によって発生した天井の高さを十二分に活かすことができます。
逆な言い方をすると、特殊な設計と言うのはこうしたアイデアがないと、無用の長物になってしまう事が往々にして多いものです。

お客さんを驚かそう
「攻防の一手」
将棋の格言に「攻防の一手」というのがあります。
一つの手が、攻めにも守りにも、あちこちに“効いて”いる、そういう1手が妙手なのだ。という意味です。
せっかくのいいアイデアでも「ここは良いんだけど、そのためにあっちにしわ寄せが・・・」では気持ちよく暮らしてゆけませんし、それ以前にたぶん実行に移す前にボツとなってしまうでしょう。
お客様をがっかりした顔にさせてはいけませんね。
設計事務所と建築家をもっと活用しよう(=こき使おう)
ひとつのアイデアが浮かんだらそれは終わりでなく、更にいいものへと価値を加えていくことで、もっと意味あるものに進化させていく。そしてある意味、奇抜なアイデアには必ず相反する問題点がセットになっているものです。それは克服しなくてはてはなりません。克服できれば、奇抜さが素晴らしい利点となって浮き出てきます。
お客様のご要望に応える時、またはアイデアをご提案する時には、ここまでの覚悟をもってそのアイデアが成功するまで、妥協無しにやり抜く。それが我々設計事務所には求められています。
というか、それを喜んでやるくらいでないと長続きはしません、実際のところ。